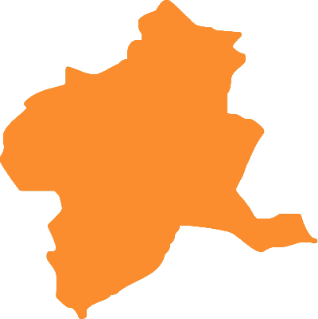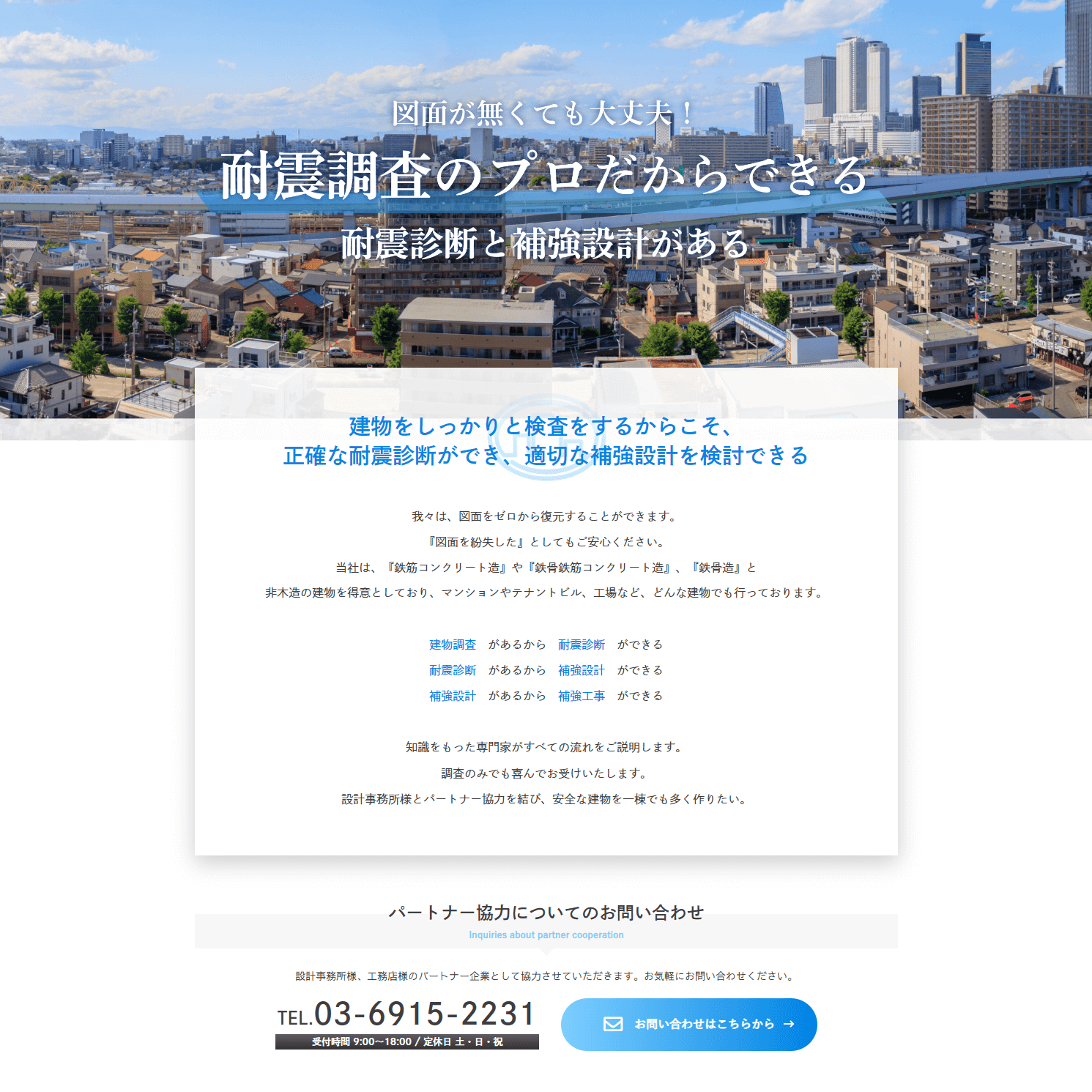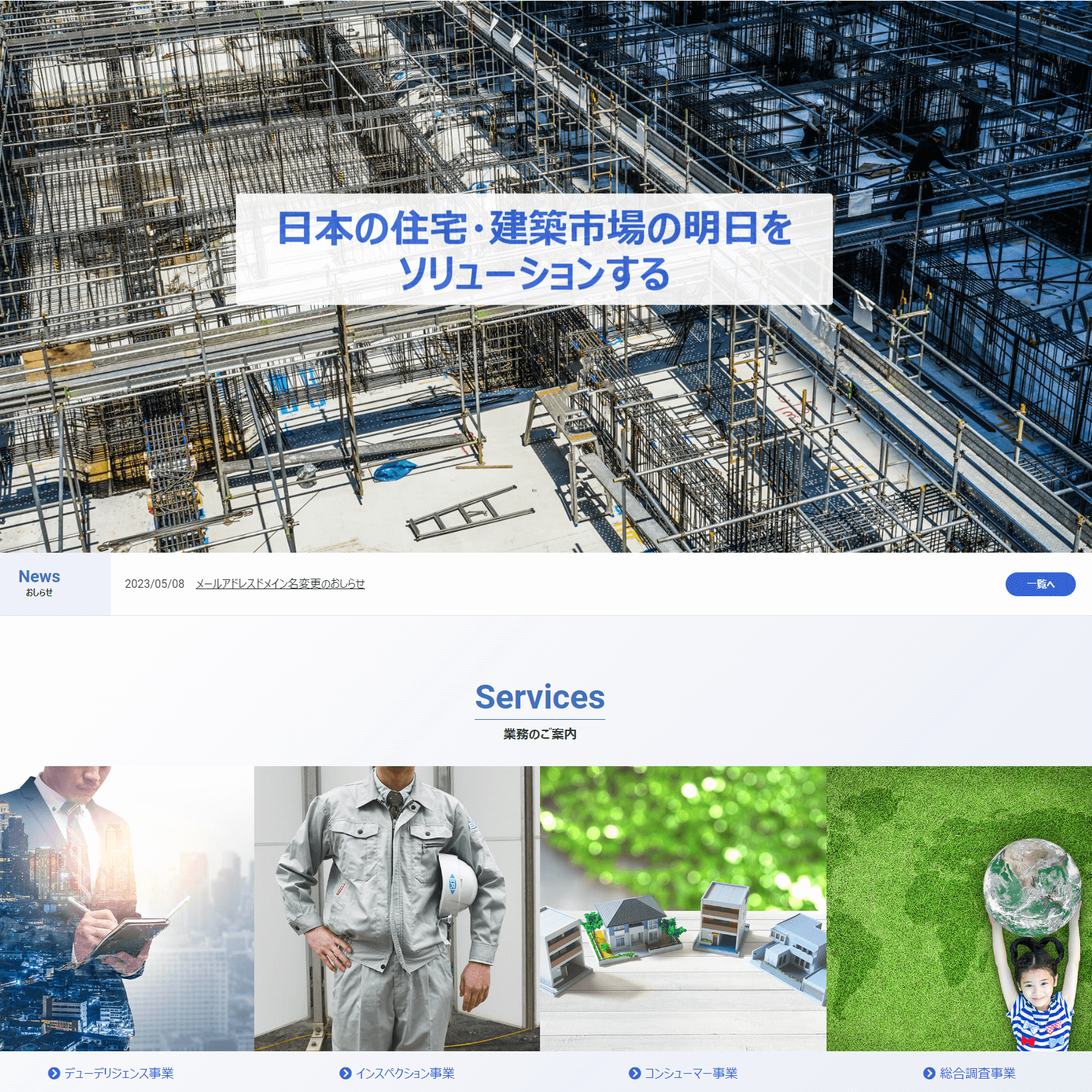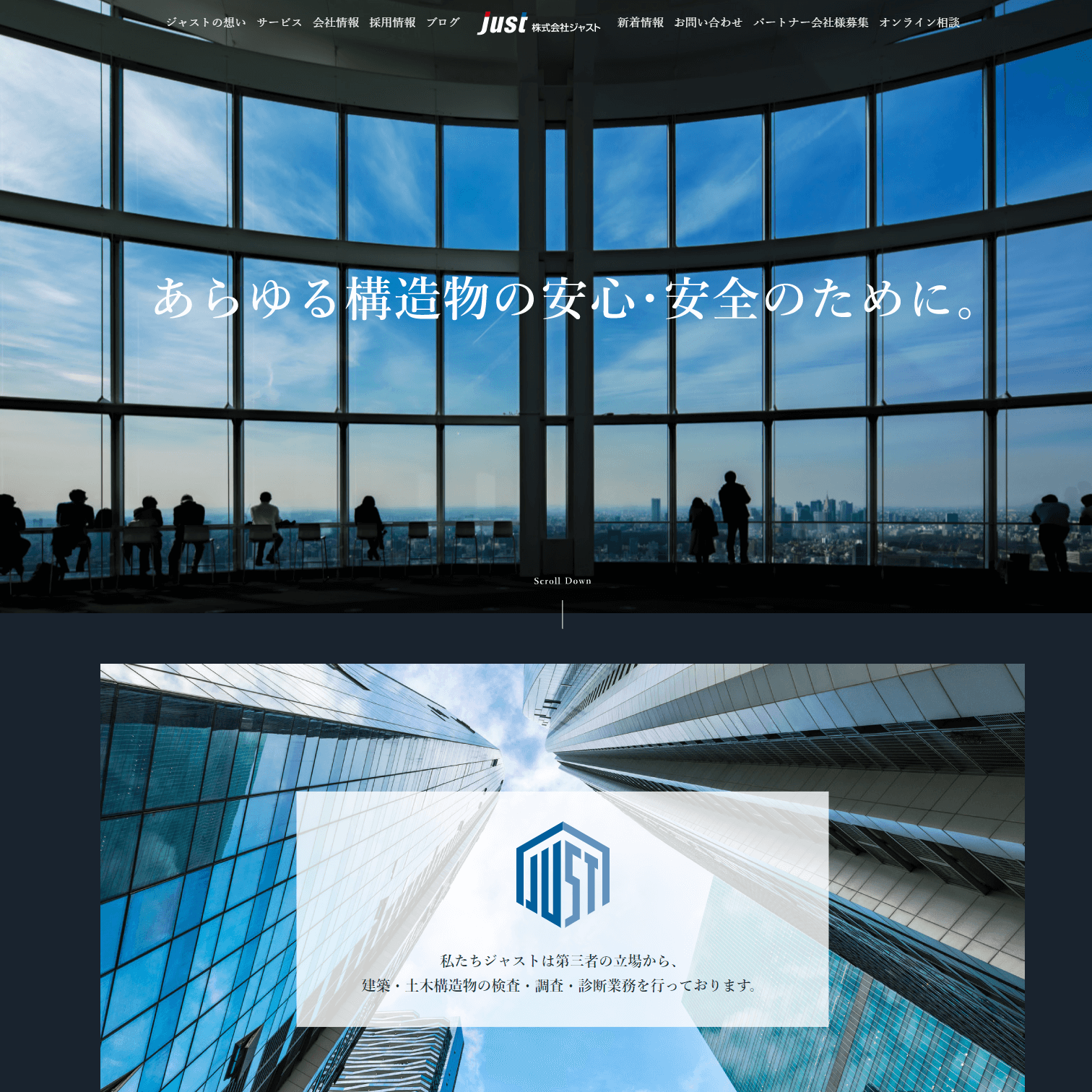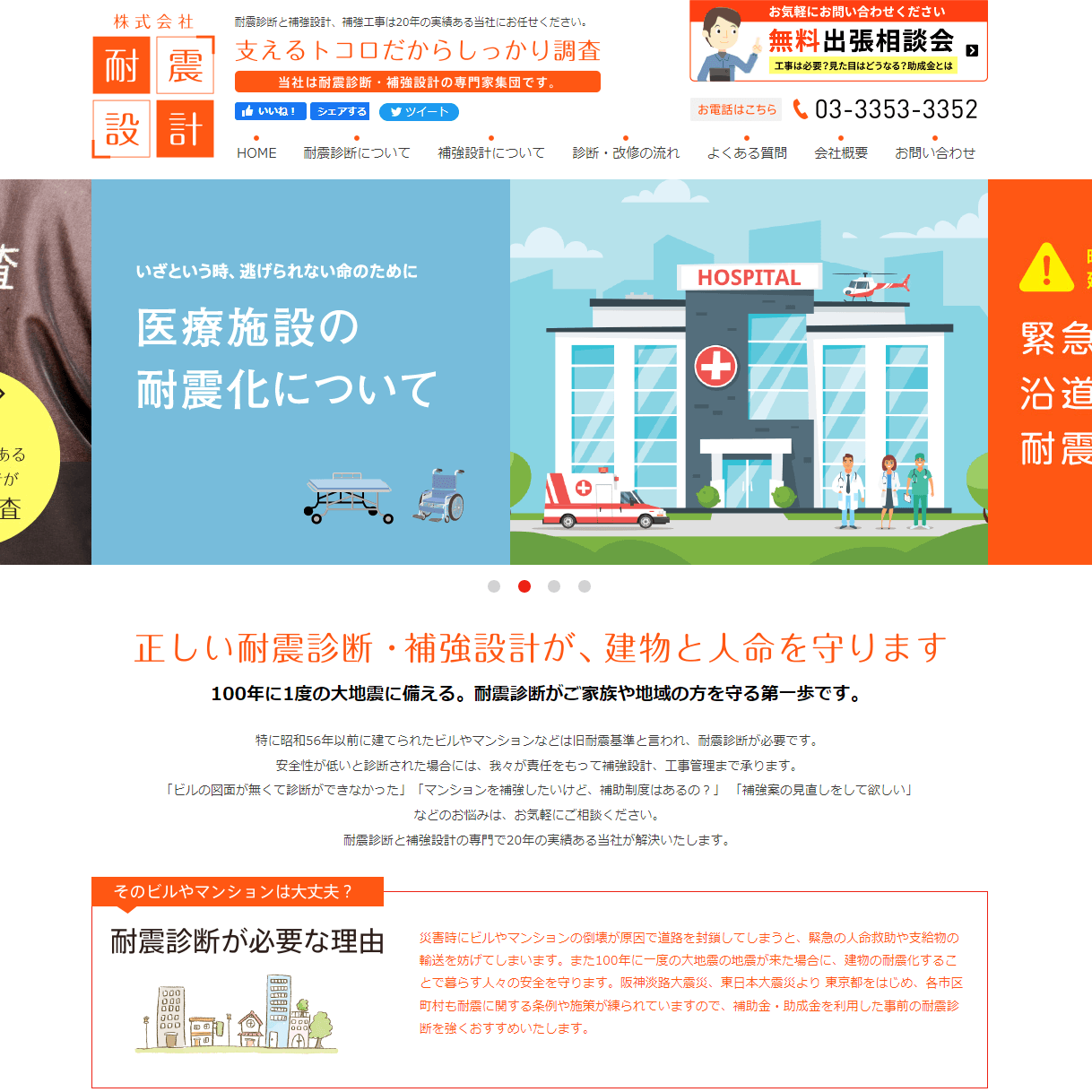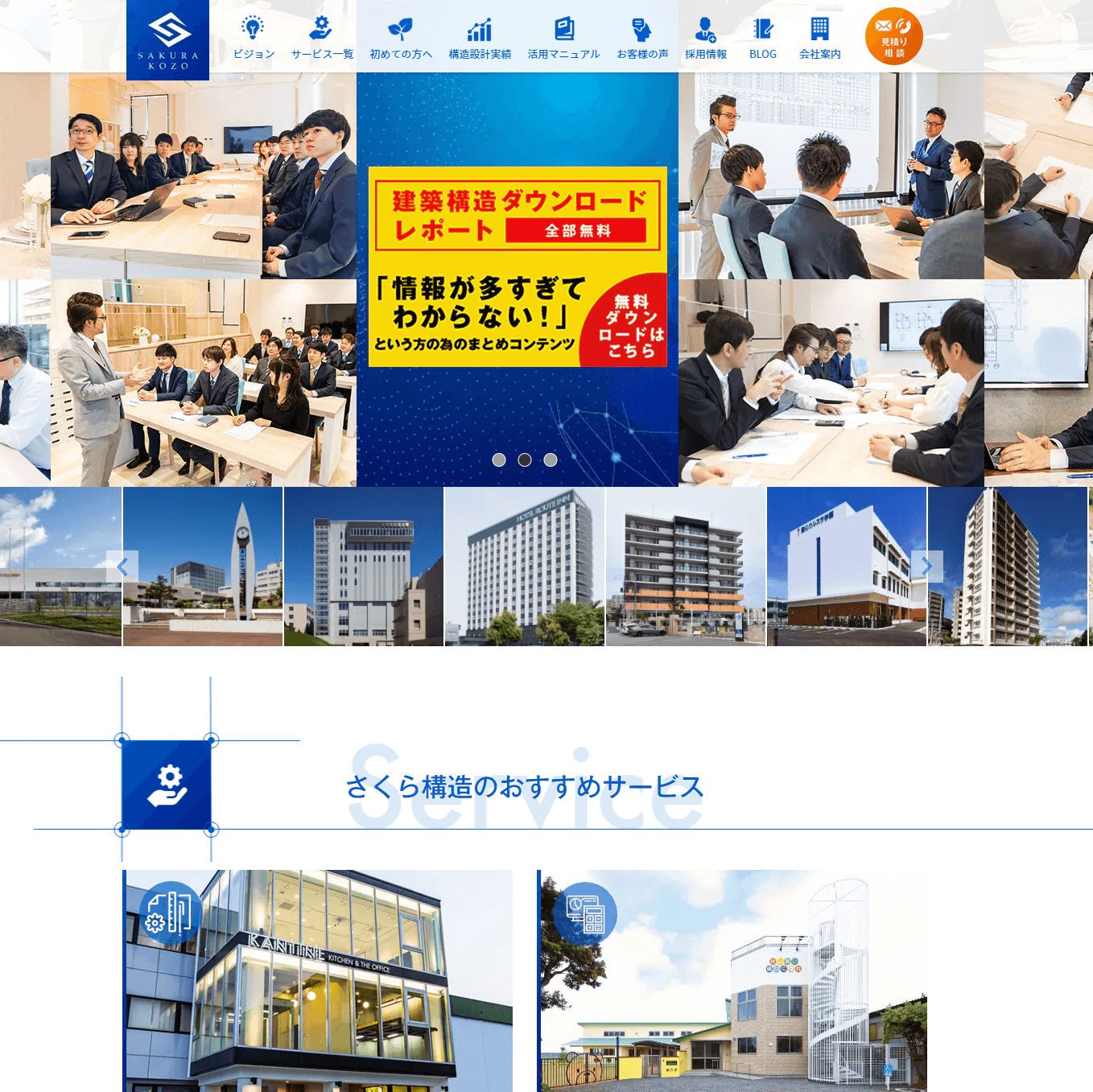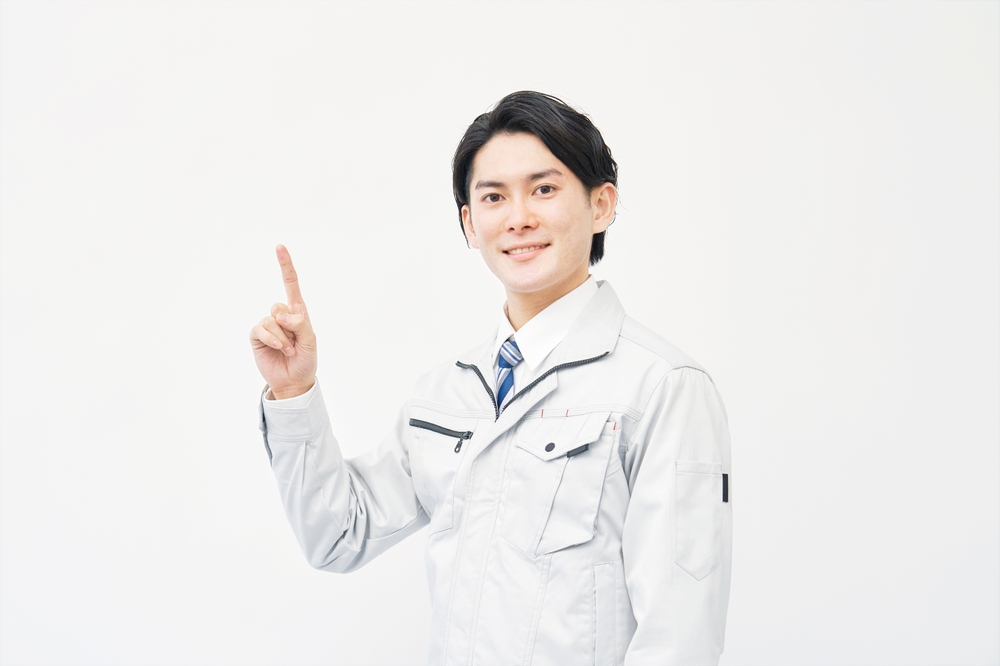耐震補強とは、建物の耐震性能を向上させる補強のことです。耐震補強をしたいけど、費用が心配という方もいるでしょう。実は、耐震補強をする際、補助金が受けられる可能性があります。耐震補強の補助金を受け取るには、条件があります。今回は耐震補強で活用できる補助金についてまとめます。
耐震補強のための補助金について
耐震補強とは、建物の耐震性能を向上させる補強のことです。1995年の阪神淡路大震災(兵庫県南部地震)後に制定された、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修法)で、建築物の耐震補強の推進が図られました。
2013年、国会で建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、以下の建物について耐震診断を実施することが義務付けられました。
・不特定多数の人が利用する建築物
・小学校
・老人ホームなどの避難弱者とされる人々が利用する建物
・大規模な火薬類の貯蔵場所
・要安全確認計画記載建築物とされた建物
不特定多数の人々が利用する建物としては、病院や店舗、旅館などが挙げられています。また、要安全確認計画記載建築物には、都道府県が指定する庁舎や避難所などの、防災拠点建築物が含まれます。
国は、耐震診断が義務付けられた建築物の所有者が実施する、耐震診断費用の一部を助成する「耐震対策緊急促進事業」を実施しています。地方自治体に補助制度がある場合は、国の補助制度と併用することができ、より多くの補助が受けられます。
ただし、窓口は該当する地方自治体に限られます。また、大学や学校に関連する建物には、文部科学省が管理している「防災機能等強化緊急特別推進事業」という補助金制度もあります。この制度は、私立大学に対してお金を支援してくれます。
ただし、審査があり、緊急性や計画の内容などが条件に合致している場合に限られます。また、耐震補強工事には、不特定多数が利用するものだけではなく、住宅を対象とするものもあります。次の項目で具体例を提示しつつ、補助金制度の内容を掘り下げます。
各地方自治体で実施されている補助金制度の例
国が実施する補助金のほかに、各自治体で補助金を交付していることがあります。ここでは自治体が実施する、補助金制度の例を紹介します。
東京都中央区「中央区建築物耐震補強等助成(木造建築物)」
東京都中央区では耐震改修・耐震診断・設計の3つのカテゴリーで、補助金を支出しています。耐震診断や補強計画は全額、耐震補強工事は一般住宅なら300万円を限度として、工事費の2分の1まで、高齢者住宅であれば同様に、300万円を限度として全額補助します。
簡易的な補強工事であっても、150万円を限度に、工事費の2分の1または、全額を補助します。
宮城県「みやぎ木造住宅耐震改修工事促進助成事業」
宮城県では、耐震改修や設計に対する補助金を支出しています。支出される補助金の額は、耐震化工事に関わる費用の3/25以内の額で、上限は15万円です。そのほかの改修工事を行う場合は、上限が25万円まで増えます。市町村によっては、工事費の1/12以内(上限7万5千円)としています。
愛知県名古屋市「木造住宅右耐震改修助成」
名古屋市の場合、一般世帯か非課税世帯かによって補助率が異なります。一般世帯の場合、工事費の4/5以内、上限100万円まで補助します。非課税世帯の場合、4/5以内、上限150万円まで補助します。
大阪府大阪市「大阪市耐震診断・改修補助事業」
大阪市では、耐震改修・耐震診断・設計の3分野で補助金を支出しています。補助率は、実施する内容によって異なります。診断の場合、補助割合は10/11までで、上限が1戸あたり5万円、1棟あたり20万円です。
設計の場合の補助割合は、2/3以内で、上限が1戸あたり10万円、1棟あたり18万円です。改修の補助割合は、1/2以内で、1戸あたりでも1棟あたりでも100万円が限度となります。なお、大阪市では、除却についても1/3以内、1戸あたり50万円、1棟あたり100万円の補助金を出しています。
以上のように、補助金の対象や金額は、自治体によってかなり幅があります。耐震補強を検討するのであれば、自分が住む自治体の補助率をしっかり調べておく必要があります。
補助金の対象となる条件は?
耐震補強の補助預金対象となるには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。主な条件は以下のとおりです。
・築年数
・建物の構造
・建物の用途
築年数の基準となるのは、昭和56年(1981年)です。この年に耐震基準が改められているため、旧耐震基準で建てられた昭和56年以前の住宅は、新耐震基準を満たしていない可能性があります。
そのため、耐震補強が必要な住宅とみなされ、補助金の対象となるのです。建物の構造という点では、木造軸組み工法で建てられた、2階以下の住宅が補助金対象となります。木造軸組み構造は、日本の一般的な家屋に用いられている工法であるため、2階以下の木造一般住宅と読み替えても差し支えありません。
建物の用途については、戸建て住宅であれば補助金対象となる可能性が高いですが、賃貸住宅であれば、建物の所有者が耐震診断することが条件となります。
まとめ
今回は、耐震補強に活用できる補助金と題して、補助金の概要や現在交付されている補助金について整理しました。昭和56年以前に建てられた木造一般住宅であれば、高い確率で補助の対象となります。自宅がこの条件にあてはまっていれば、補助金を申請したうえで、専門家による耐震診断などを受けてみてはいかがでしょうか。
-
 引用元:https://taishin-beri.jp/
引用元:https://taishin-beri.jp/
耐震診断についてわからない方も、とりあえずこの会社
診断実績豊富&図面なしでも診断可能