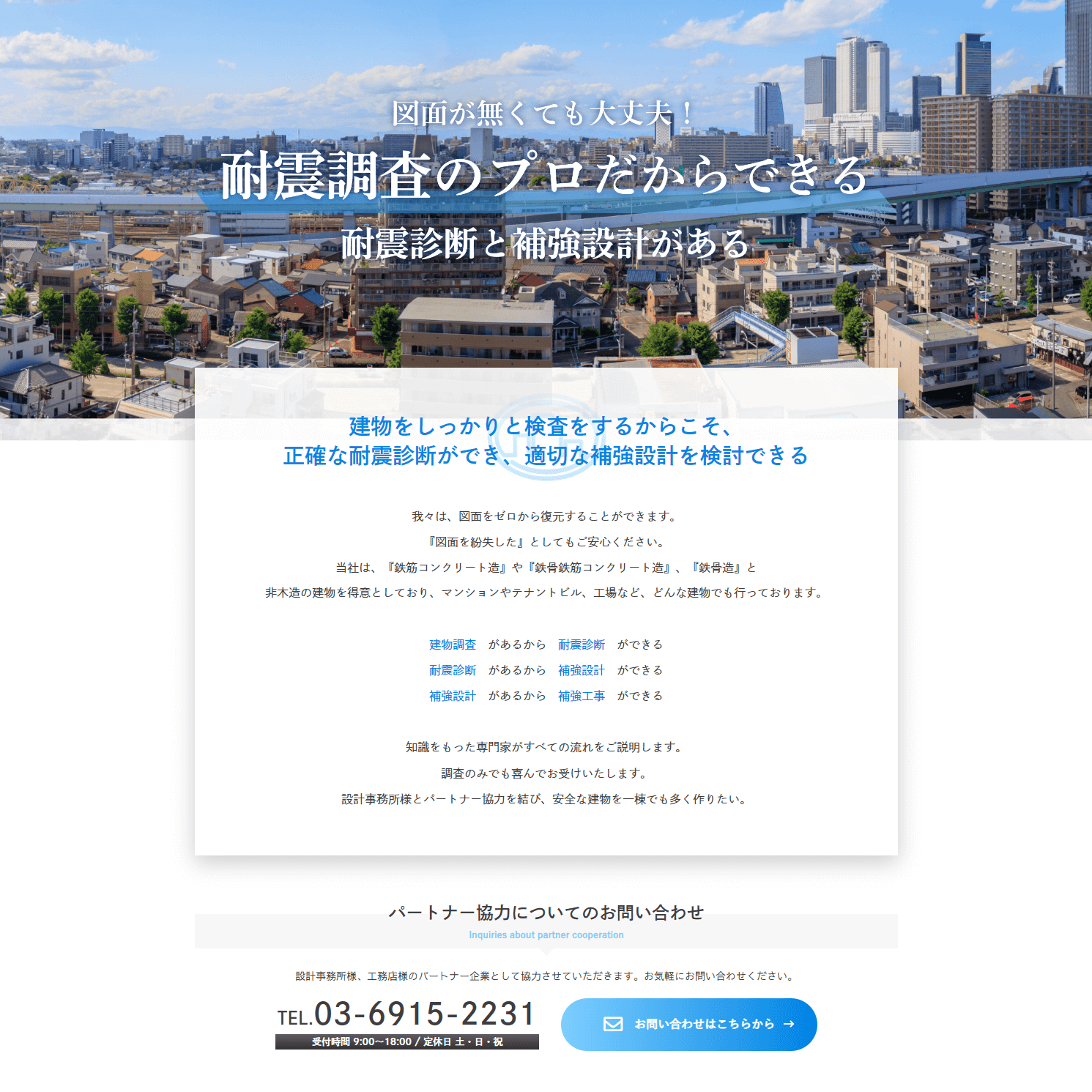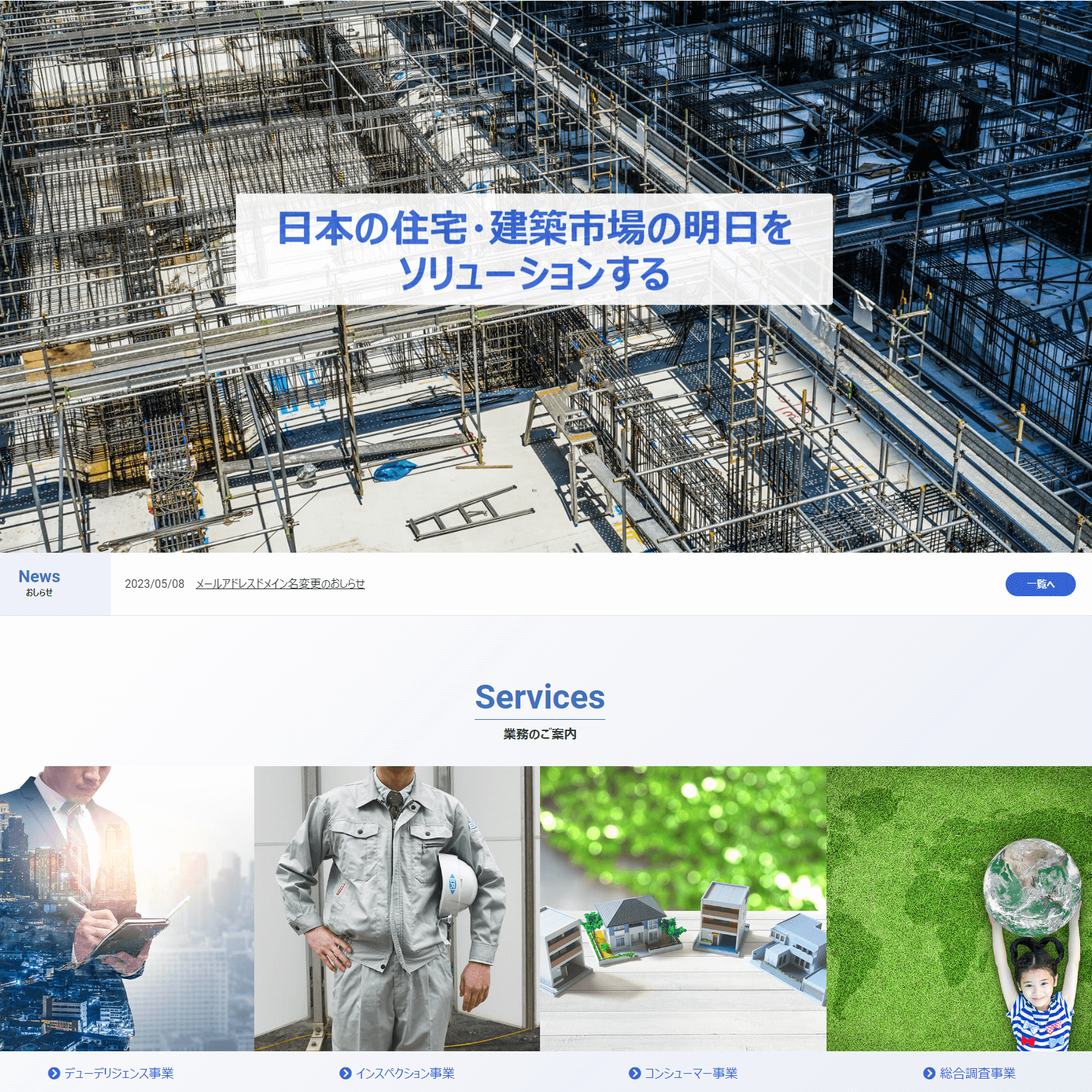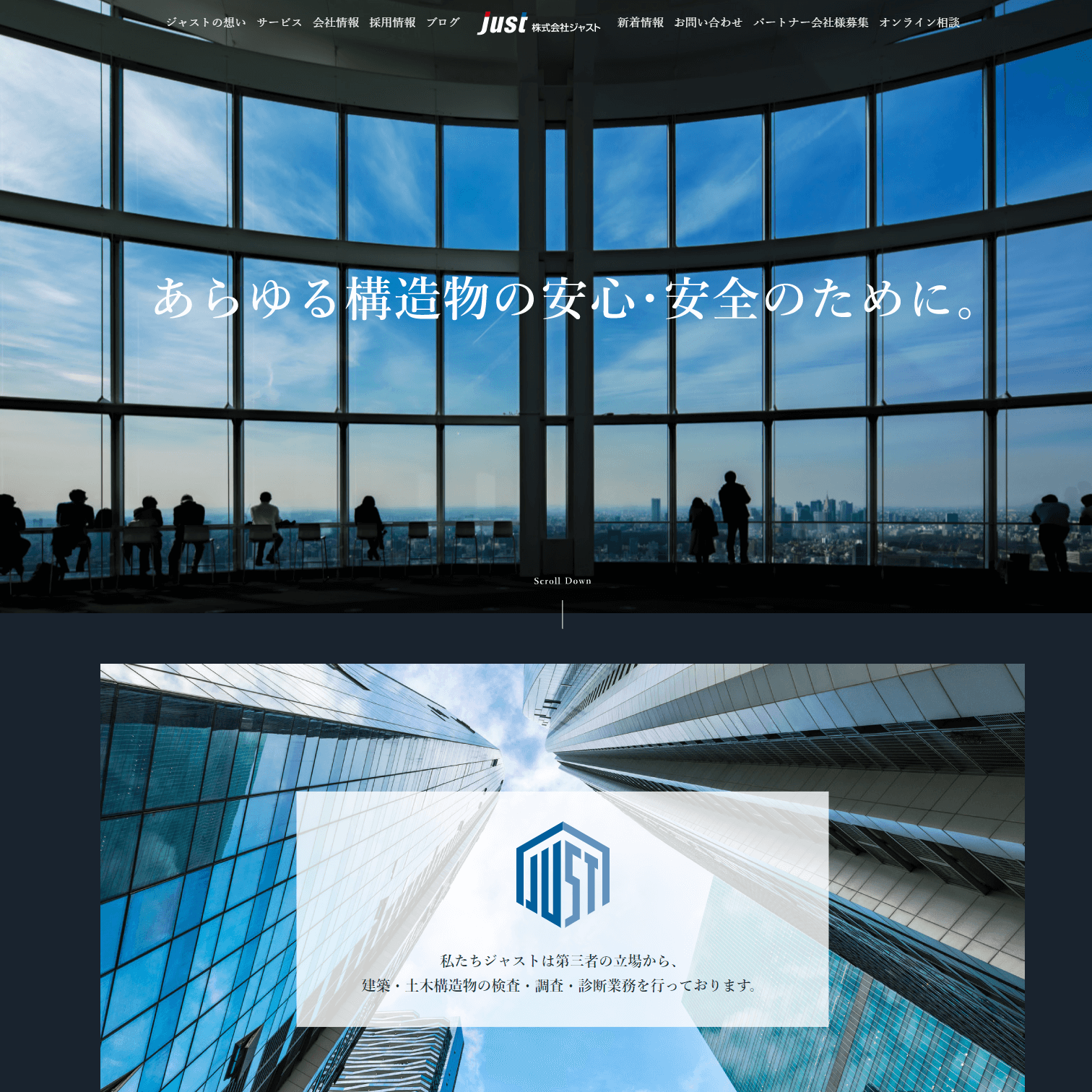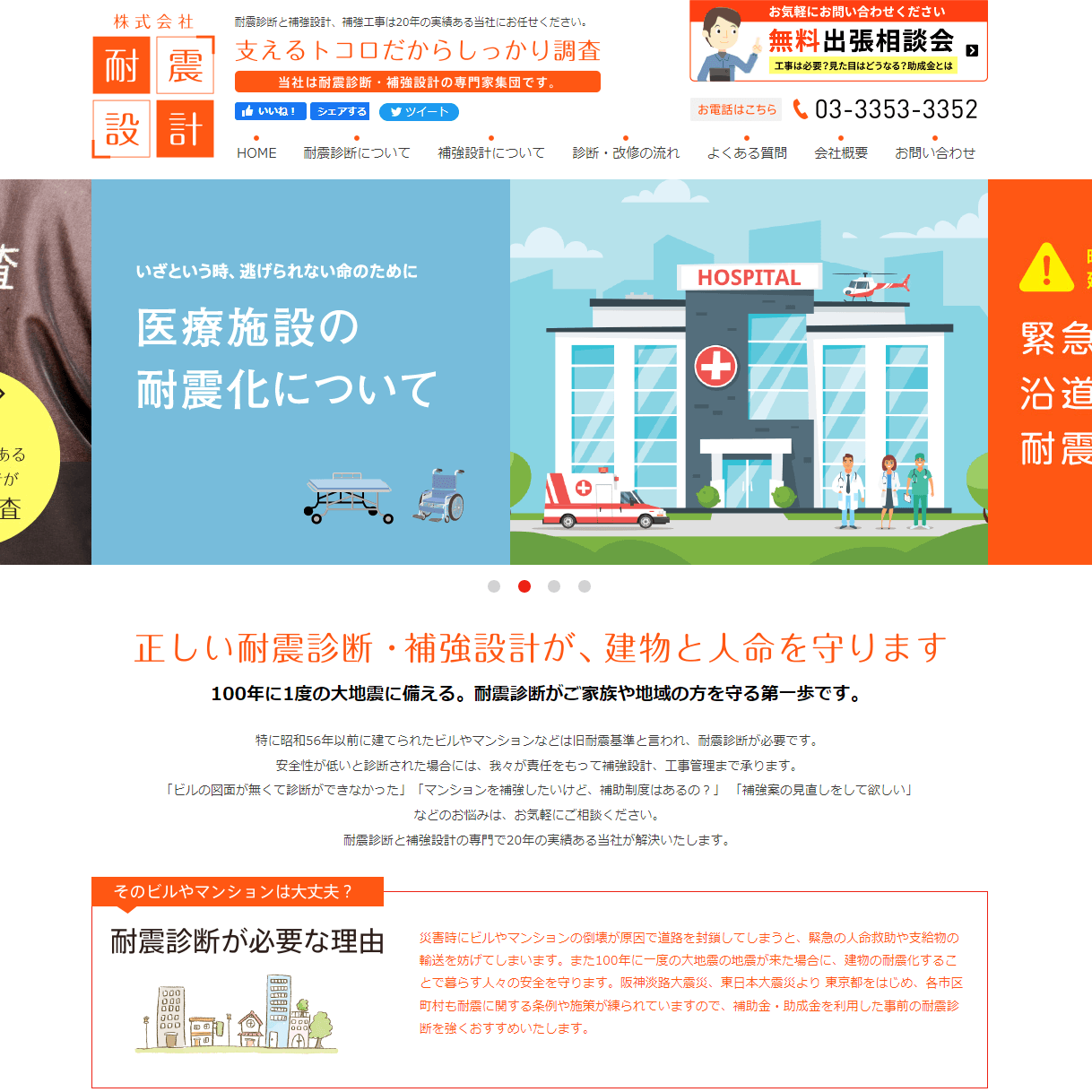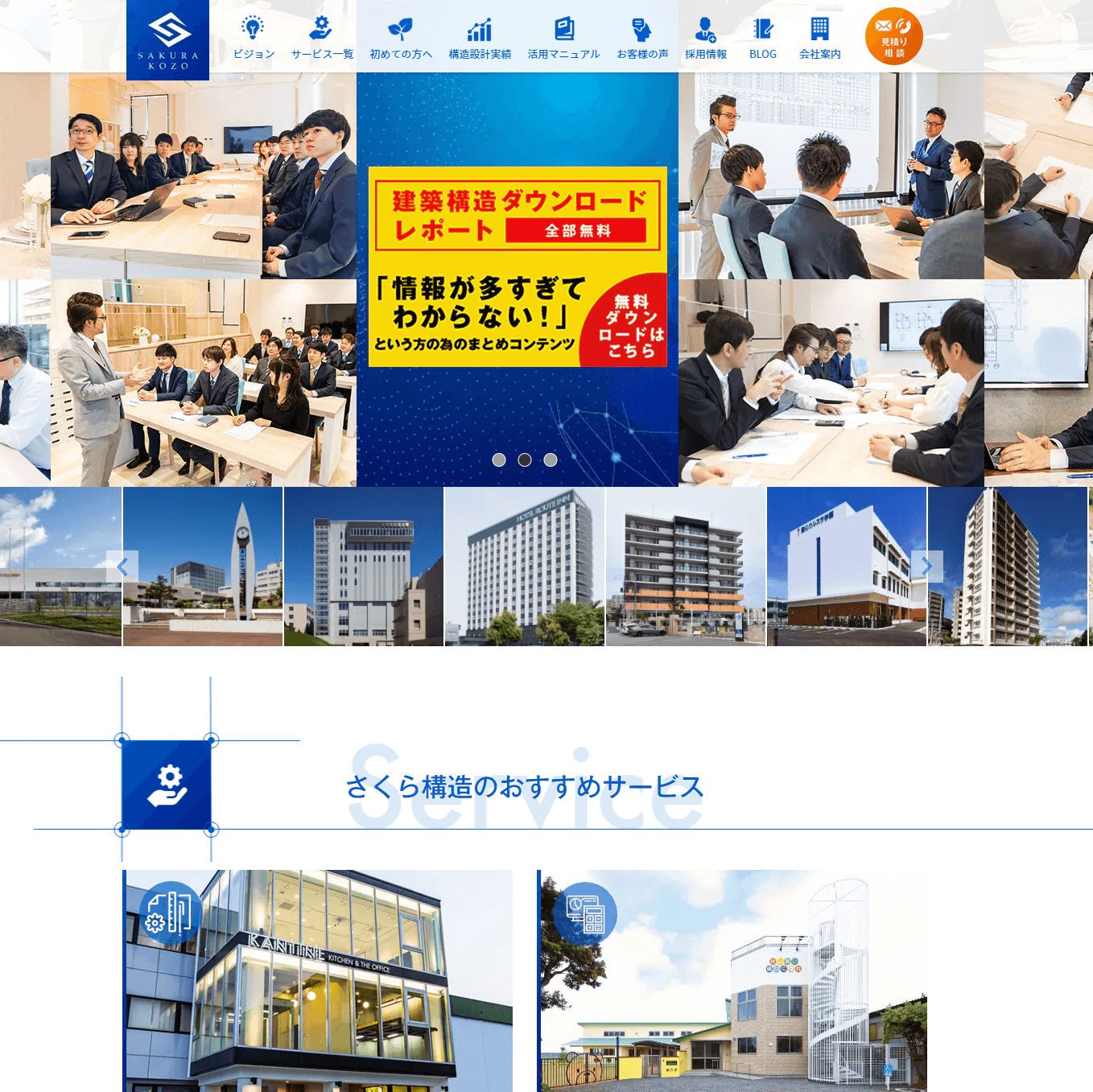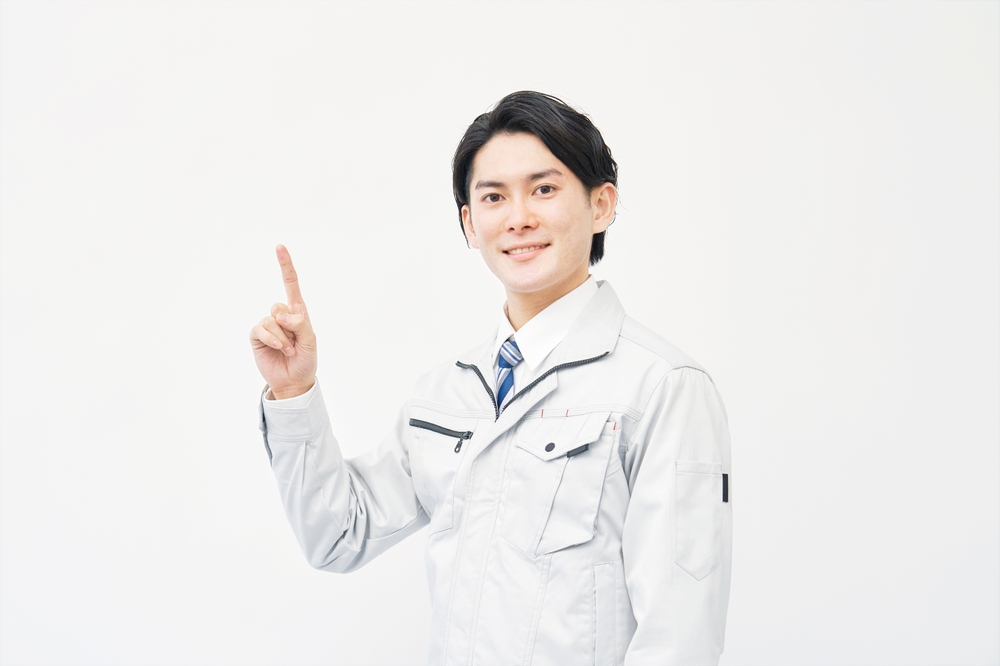住宅には耐震基準とは別に「耐震等級」というものが存在します。自宅の耐震等級は、安心・安全に暮らすためには欠かせない要素です。そこで本記事では、耐震等級が決まる要素やその基準、自宅の耐震等級を調べる方法をまとめて紹介します。いざというときに備えるためにも、ぜひご一読ください。
耐震等級を決定する4つの要素
耐震等級を決める主な要素は、以下の通りです。順番にその内容を見ていきましょう。
建物の重さ
まず、建物の重さは構造材によって異なります。とくに瓦屋根のような重い屋根は地震の影響を受けやすいため、軽量の屋根材や金属サイディングなどを使って建物全体の重量を抑える工夫が重要です。
耐力壁と柱の数
耐力壁とは、地震や暴風による水平方向の力に抵抗する壁のことです。通常の壁に筋交いや構造用合板を使って補強し、強度を高めています。一方、柱は垂直方向の力に耐える役割を持ち、これらの耐力壁や柱の数が多いほど建物は強固になります。
耐力壁の配置
しかし耐力壁は単に多ければ良いわけではなく、耐力壁の配置も重要です。配置に偏りがあると耐震性が下がる恐れがあります。建物の隅だけでなく、方角や向きに偏りなく均等に配置し、2階建ての場合は1階と2階の耐力壁の位置を合わせることで、地震の力を効率よく分散可能になります。
基礎・床の耐震性
基礎は建物にかかる力を地面に伝える役割を持ち、基礎が弱いとどんなに上部構造が強くても建物は壊れやすくなります。また、床の強度も重要で、例えば吹き抜けなどで床が弱いと地震時に大きく変形し、耐震性能が低下します。基礎や床の補強は建築段階で行うことが望ましいです。
耐震等級の基準
耐震等級は建物の耐震性能を評価する指標で、耐震等級1、2、3の3段階に分かれています。これは、数字が大きいほど高い耐震性能を示します。
耐震等級1
まず、耐震等級1は建築基準法で定められた耐震基準と同等であり、これから建てる建物は最低限この等級を満たす必要があります。具体的には、数百年に一度程度発生する地震に対して倒壊・崩壊しないこと、また数十年に一度程度発生する地震に対して損傷を生じないことを基準としています。
耐震等級2
耐震等級2は耐震等級1の1.25倍の耐震性能を持つことを示します。災害時の避難所となる学校などの公共施設はこの基準を満たす必要があります。基準の内容は、数百年に一度程度の地震に対して耐震等級1の1.25倍の力に耐え、倒壊しないこと、また数十年に一度の地震に対して1.25倍の力に耐え損傷を生じないことです。
耐震等級3
耐震等級3は現行の最高基準で、耐震等級1の1.5倍の耐震性能を持ちます。警察署や消防署など重要な施設は、この基準で設計されています。基準は、数百年に一度の地震に対して1.5倍の力に耐えて倒壊しないこと、数十年に一度の地震に対して1.5倍の力に耐え損傷を防ぐことを求めています。
自宅の耐震等級を調べる方法
自宅の耐震等級や耐震性を調べたい場合、主に以下の方法があります。自宅の状況を確認し、それに合った方法を選択してみてください。
住宅性能評価書を確認する
2000年4月の品確法施行以降に建てられた住宅であれば、住宅性能表示制度に基づく評価書が取得されている可能性が高いです。
評価書には耐震等級が明記されているため、管理会社や不動産業者、建築会社などに問い合わせて確認できます。ただし、2000年以前に建てられた住宅の場合、評価書が存在しないことが多いため、別の方法で耐震性能を調べる必要があります。
住宅性能の評価を受ける
次に、国土交通省認定の第三者機関である「登録住宅性能評価機関」に依頼し、住宅性能の評価を受ける方法があります。この方法では専門機関が建物の耐震性能を評価し、正式な評価書を発行します。
費用はおおよそ10万〜20万円程度で、依頼する機関によって異なるため、事前に見積もりを確認してから依頼することが重要です。
耐震診断を受ける
建築基準法に基づく耐震性能の調査として「耐震診断」を受ける方法もあります。耐震診断にはセルフチェック、専門家による一般診断、補強工事を前提とした精密診断の3段階があります。
まずは自分でセルフチェックを行い、建物のどの部分が地震に対して強いか弱いかを把握することが推奨されます。
その後、必要に応じて専門家に一般診断や精密診断を依頼すると良いでしょう。これらの診断は建物の耐震性を具体的に把握し、必要な補強や対策を検討するうえで役立ちます。
まとめ
住宅の耐震等級は、地震に対する建物の強さを示す重要な指標です。建物の重さや耐力壁・柱の数と配置、基礎・床の構造といった4つの要素から決まり、等級は1〜3の3段階です。等級が高いほど耐震性が高く、等級3は警察署や消防署などにも採用されています。自宅の等級を調べるには、評価書の確認や専門機関による診断が有効です。とくに2000年以前の住宅では評価書がないことが多く、専門家による診断が必要になる場合もあります。自分でセルフチェックを行う方法もあるため、まずは現状を把握することから始めてみましょう。安心・安全な暮らしを守るためにも、耐震等級の理解と確認は早めに行うことが大切です。
-
 引用元:https://taishin-beri.jp/
引用元:https://taishin-beri.jp/
耐震診断についてわからない方も、とりあえずこの会社
診断実績豊富&図面なしでも診断可能